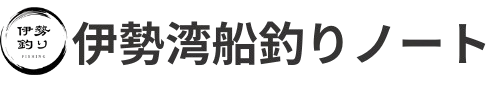船釣りと聞いたら身構える方が多いのではないでしょうか。船に乗ったことはないけど、船釣りに挑戦してみたい!けど分からないことが多すぎて心配・・・。そういった方を対象に船の予約から持ち物、当日の動きまで丁寧にお伝えしていきます!
船釣りとは
船釣りについて知ろう
陸からの釣りである「おかっぱり」と対比して「沖釣り」や「オフショアフィッシング」と呼ばれています。
特徴として、船で沖に出て船上から釣りを楽しめます。船長が魚群探知機を使って魚の居場所を特定し、効率的に釣りを楽しむことができます。
種類は大きく分けて、「乗合船」と「仕立て船」に分かれており、乗合船では船宿が設定した釣り物や日時で、釣り人が自由に集まり乗る方式です。仕立て船は逆に、仲間を集めて船をチャーターして、釣り物を自由に選択できる形式です。
釣り物を決めよう
好きな魚を選ぼう
まずは、やってみたい釣り物を探してみることから始めましょう。釣りの種類は様々あり、初心者におすすめな釣りから難しい釣りまで様々です。中でもおすすめなのは、アジやイサキ・キスや天秤太刀魚など比較的小物な魚を狙うことをお勧めします。筆者は初めての釣りでLTアジ(ライトアジ)に行き、船釣りにはまりました。
難しい釣りに注意しよう
一見すると、スーパーなどでよく見かける魚でも釣りとなると難しいことがあります。
特に、大型魚が対象の釣りはやめておくことが無難です。また、特殊な仕掛けの釣りにも注意しましょう。仕掛けの全長が長いスルメイカや、太刀魚テンヤやエギタコのようなルアーを買うような釣りは最初は避けておいたほうが良いです。
船宿を予約しよう
船宿を探してみよう
釣り物が決まったら船宿を探しましょう。逆に、自分が行きやすい地域の船宿を探して、そこから釣り物を決めるもの良いと思います。それぞれの船宿では、季節にあった魚や現在釣果が伸びている魚をターゲットに船を出しているところが多いです。
船宿の探し方
現在では、ネットが発達したためブログやSNS、各船宿サイトから探すことができます。また、大手チェーン釣具屋では船の名刺や広告を掲載しているところも多く、店員さんに聞いて探すことも方法の一つです。例えば愛知の港から出ようと思っている方であれば、「伊良子沖 釣船」や「大山沖 釣船」などで検索するとヒットしやすいです。また、グーグルマップなどの口コミを見てから決めたほうがいいかもしれません。
予約をしよう
船宿と釣り物が決まったら予約をしてみましょう。予約したい日程と釣り物を電話で伝えてみましょう。席が空いていれば予約はできます。予約時には必ず「初めてであること」を伝えておきましょう。その後のやり取りがスムーズになると思います。また、ロットやリールなどを借りる場合はここで伝えておくことが無難です。貸し竿は1000円~2000円が相場になります。道具については後に説明します。
車で向かう際には駐車場や集合場所などを聞いておくと、当日スムーズに船までたどりつけると思います。
当日の流れについて
基本的には指定時間の30分~1時間前に指定場所に到着することがマナーです。初めての船宿に行く場合、筆者は2時間前には近辺に到着しコンビニなどで時間を潰していることが多いです。予定時間の1時間前にはお客さんも集まってくるため、様子を見て集合場所に行きましょう。船長さんや女将さんに名前を伝えるとその後の動きを教えてもらえます。また、天候悪化に基づき釣船が出れない場合があります。船宿によって様々ですが前日の夜に電話を入れてくれる船宿さんや当日の朝に連絡が入るところなど様々です。
船釣りの持ち物について
服装について
アウトドアのため、天候に大きく左右されます。夏は脱いだらある程度調整できますが、海上の冬は思っている以上に寒いです。防寒着を多めに着込んでいくことをお勧めします。また、水しぶきや魚のなどで服が濡れてしまいます。濡れてもいい服装を持ち込み、万が一のために雨具を持参するとよいでしょう。また、靴は長靴などを履いたり夏であれば滑らないサンダルとかでもよいかもしれません。
持参する道具
基本的にレンタルロットの場合は、クーラーボックスは最低限持っていきましょう。また、いろいろな道具があると便利になるため、おすすめの道具をまとめます。
クーラーボックス

誰でも鮮度よく魚を持って帰りたいですよね。そのためにまずはクーラーボックスを準備しましょう。釣具屋さんではDAIWAやSIMANOのメーカーのクーラーボックスが売っていますがとても高価です。最低でも20L以上は持参したいところですがメーカー品を使うと最低1万円以上はします。最初そこまでお金をかけたくない人は、ホームセンターで気持ち大きめのクーラーボックスを購入し沢山氷を入れておきましょう。コンビニのブロック氷などは高価なため、筆者や家で空のペットボトルに水を入れて凍らせて持参しています。船に乗ったら、海水を軽く入れて冷やしておくと良いですね。
フィッシュグリップ

フィッシュグリップとは、魚をつかむためのトングです。魚のヒレなどには鋭い棘がある場合があり手に刺さると地味に痛いです。魚を掴むのはコツがいりますが慣れたらスムーズに持てると思います。
ゴミ袋
ほとんどの船宿さんはゴミを捨てるところがありません。仕掛けのパッケージなど思っている以上にゴミが出るため、ゴミ袋を持参すると後片付けがスムーズになります。
気を付けるポイント
船長の指示を聞こう
船長の指示は絶対
船釣りでは、船長がマイクで様々な指示を出します。必ず守りましょう。特に、「巻いてください」「流します」といった指示は船を動かしますよという指示のため、仕掛けを巻いてあげましょう。また、船によって使う仕掛けの種類や重りの号数が決められていることが多いです。ルールを守らないとお祭りの原因となったりするので必ず指示に従いましょう。
指示がわからない場合は
初めてで、指示がわからない場合は中乗りさんや周りのお客さんに気兼ねなく聞いてみましょう。基本的には、教えてくれるケースが多いです。また、釣り方が分からなかったりした場合にも同様に中乗りさんに聞いてみると良いでしょう。周りのお客さんとのコミュニケーションも大事なことです。
船釣り時のマナーについて
オマツリをしてしまったら
オマツリとは、仕掛けがほかの人と絡んでしまうことを指します。船のルールに従いましょう。魚がかかっている人が優先的に仕掛けを上げる、道糸(リールに巻いてあるカラーがついているライン)と仕掛けが絡んでしまって取れない場合は仕掛け側を切るなどが基本的なルールです。オマツリをしてしまっても「すいません」などと謝れば問題なく終わるケースがほとんどです。何度も自分だけ他の人とオマツリをしてしまうのであれば、周りの人にどうやったらオマツリをしなくなるのか聞いてみる方法もあります。
根掛かりをしてしまったら
根掛かりとは、海の底で重りや仕掛けが岩の隙間や海藻などに絡んでしまいラインが巻けない状態を指します。船を流している船宿であれば仕掛けが動かないためオマツリの原因になります。まずは、船長や中乗りさんを呼びましょう。竿で無理やり引き抜くと竿の先端が折れる可能性がありますので絶対にやめましょう。根掛かりをとるコツはありますが、初めてでは難しいため仕掛けが切れる覚悟で外します。自分で引き抜く際には、ラインをペットボトルなどに巻き付けて引き抜きましょう。素手でやると手が切れる恐れがありますのでやめたほうが無難です。
釣り座について
釣り座とは船の席のことを指し、釣りをする場所です。船宿によって様々なルールがあり、大きく分けてくじ引きか先着順です。くじ引きではお客さんみんなでくじを引いて1番のお客さんから好きな席をとっていきます。先着順では、早く来たお客さんから席をとっていくルールです。初心者の方は船長の目が届くところを選びましょう。事前に船長に伝えていれば近くに案内されるケースが多いです。
喫煙について
釣りをしながら喫煙できるかどうかは船のルールに従いましょう。筆者が行く船ではほとんどが喫煙可能です。中乗りさんが煙草を吸いながら仕事をしているなんてこともあります・・。自分の場合は慣習として特に気にしていませんが、逆に喫煙者の方は周りが吸っているのか否かをまず確認しましょう。周りが吸っていれば、吸っていても言われることはありません。吸殻を海に捨てるのは絶対にやめましょう。灰皿などを持参し、環境に配慮しましょう。環境があるからこその船釣りということを忘れてはいけません。
周りのお客さんとコミュニケーションを取ろう
自分が釣りをしている左右には他のお客さんが座っているはずです。まず、座席についたら左右のお客さんに「よろしくお願いします」などと声をかけましょう。年配の方なら世間話しなどをすることも多々あります。コミュニケーションを取っておくと、釣り方が分からなかったりオマツリをしてしまった時など聞きやすくなると思います。初心者の頃は、周りのお客さんからおすすめの船宿や釣り物を聞くことが多かったです。釣りが好きなため話が弾むことも多く、面白いですよ。
最後に
初心者のうちは何が何だか分からないと思います。初心者のうちは釣れたことでまず嬉しくなると思います。「なんか釣れた」から、誘いなどを覚えていくと「釣ってやった」といった感覚に代わっていきます。何を重視して釣りをするかは人それぞれですが、誘いを覚えて周りのお客さんよりも釣れるようになっていくと面白さも倍増します。まずは、釣りを楽しんでみてください!